お子さんが中学3年生になると、高校入試のことが気になってきますね。テストの成績、志望校の選択、塾選びの情報など、受験に関する話題が増えたのではないでしょうか。
「○○さんは、もう塾に通いだしたようよ。」とか……。
入試はまだ先のことだからとゆっくりしていると、あとで慌てることになりかねません。
実際、勉強のスタートが遅くて、学力が伸び悩む例をよく耳にします。
中3年生になったら、まず受験までの学習計画を立てて、早く受験勉強に手を付けることをお薦めします。受験勉強はやはり時間がかかりますし、また時間をかけないと実力が身につかないからです。
「少しでも早く始めること」「計画的に学習を進めること」が、実力をつける一番確実な方法なのです。
ここでは、学習計画をどのように考えたらよいか悩んでいる方のために、学習計画の立て方を説明させていただきます。
塾で実施している実績のある内容であるため、参考にしていただけますと幸いです。
1.学習計画は立てるときは2つのことに気を付けましょう
学習計画を考える時に気をつけてほしいことが2つあります。以下の2つです。
- 入試までの1年間を通して計画を考えること
- 日程的に余裕のある計画にすること
まず、この2つのことから説明させていただきます。
1-1.春から入試までの全体的な計画を考えることがたいせつです
受験勉強の学習計画は、春から入試までの日程を逆算して、全体を見渡して考えましょう。
期間を区切って、それぞれの期間に何をするべきかを考えていくと、効果的な計画をまとめることができるからです。
受験勉強はまず、基礎をしっかり固めることがたいせつです。
そして、基礎から段階的に学習を積み上げていく必要があります。いきなり難しい問題と取り組んでも、時間ばかりかかってうまくいきません。
一般的には1学期、夏休み、2学期、冬休み、3学期の5つの区切りで考えるといいです。学校生活のサイクルと合わせられるので、学習内容の切り替えやスケジュールの管理がしやすくなります。
年度の途中で計画を考える場合は、この区切りを基にして、状況に応じた修正を加えてください。
学習計画の基本は、入試までの「どの時期」に、「何をすれば良いのか」がはっきりわかるように決めることです。階段状に学力を上げていくことを、イメージしていただくとよいと思います。
1-2.日程的に余裕のある計画にしましょう
5つの期間に区切った計画は、さらに月単位や週単位で、より具体的に「何を」「どれだけ」するのか、決める必要があります。
その際に気をつけることは、日程的に余裕がある計画にすることです。
勉強の進み具合は一人ひとりで異なります。
ある部分で手間取ってしまったり、以前の範囲に戻って復習する必要がでてきたりすることもあります。それらの状況に合わせて、微調整しやすくするために、あらかじめ余裕を持たせておくのです。
たとえば、日曜日は何も予定をいれないで、遅れを取り戻す「予備日」と考えておくとよいでしょう。
受験勉強は実際にやりだしてみると、たいていは想定したよりも時間がかかります。
特に、勉強を始めた当初は、勉強に慣れていなかったり、忘れていることが多くあったりして、思うようにはかどらないものです。
あらかじめ、ある程度の「遅れ」を見込んで、余裕がある計画にしておきましょう。
2.1年を5つの期間に区切ってやるべきことを考えましょう
それでは、具体的に1年間を、先に解説させていただいた、5つの期間に区切って考えてみましょう。
以下のように、それぞれの期間で「テーマ」を決めて、「何をすればよいか?」を考えるとよいでしょう。
- 1学期-「基礎復習期」
- 夏休み-「学力養成期」
- 2学期-「実力充実期」
- 冬休み-「実戦演習期」
- 3学期-「直前対策期」
2-1.1学期は基礎固めに重点をおきましょう
1学期には、1,2年の復習をひと通りでいいです。そのため、ざっとすませましょう。
1年生や2年生のときに習った内容があやふやだと、これからの受験勉強の効率が悪いからです。
特に英語や数学は積み重ねの教科ですから、基礎をしっかりさせることが重要ですね。
たとえば、薄い問題集を使って、基礎、基本のレベルの問題だけを一巡する方法がよいでしょう。本格的な学習は夏以降に取り組むとして、この時期は応用、発展問題にはこだわらなくて大丈夫です。
夏以降の学習を効果的に進めるために、1学期は自分の弱点や課題を見つける時期と考えてください。
1,2年の全範囲をひと通り復習しておくことが重要なのです。
2-2.夏休みで確実に実力をつけましょう
夏休みは1年の中で、一番学習効果があがる時期です。朝から晩まで、できる限り、全力で勉強をしましょう。
夏休みは、およそ6週間にわたって、自由に時間が使えます。
これほどの長期間、自分のペースで、自分に必要な勉強をすることができるときは、夏休みをおいて他にありません。
ぜがひでも、効果的な学習をしなければなりません。
内容としては、まず、1学期の復習で感じた苦手科目や弱点を、集中的に復習して克服しておきましょう。
ここで弱点を克服しておくと、2学期以降の勉強がスムーズに進められます。
過去の実績からみて、夏休みの過ごし方は、2学期以降の勉強、ひいては受験の成否に大きく影響します。
夏休み期間は、何が何でも弱点を克服する心構えで、目いっぱい勉強してください。
勉強時間の目安は、午前3時間、午後3時間、夜2時間の合計8時間です。
時間をかければよいということではありませんが、しっかりと復習しようと思えば、これくらいの時間は必要です。
これも経験から感じることですが、「夏にかけた時間が、冬に実力となって還ってくる」ので、ぜひ、全力を尽くしてください。
2-3.2学期はペースを守って根気よく続けましょう
2学期はほぼ4ヶ月間あって、期間の区切りとしては一番長い期間になります。期間が長くて気候もいい時期なので、たくさん勉強できるのが特徴です。
その反面、勉強のペースが崩れないよう、勉強の意欲が落ちないように気をつける必要があります。
2学期には文化祭や体育祭、合唱コンクールなど、学校の行事が多くあります。それらに時間が取られたり、勉強に集中しにくくなったりするからです。
1学期は新鮮味があります。
夏休みは集中できます。
冬休み以降は自然と力が入ります。
行事の影響などで勉強が遅れやすいのが、この2学期なのです。
途中で長期の休みもありませんので、月単位や週単位でのスケジュール管理を、意識的にしっかりやる必要があります。予定どおり進められないところは、日曜日などを使って追いつくようにしないといけません。
2学期はペースが乱れで「中だるみ」にならないよう、特に気を付けてください。
行事や活動に惑わされることなく、着実に勉強を積み重ねなければならない、大切な期間です。
2-4.冬休みから実戦期に入ります
冬休みからは、より入試に近い内容を演習する、「実戦演習期間」と考えます。自分のペースで、自由に時間が使える時に、自分に必要な勉強と取り組みましょう。
この時期になると、かなり力がついているはずですので、応用問題や過去問に挑戦するのもいいでしょう。
あるいは、集中して単語を暗記したり、理科、社会の一問一答に取り組んだり、いろいろと工夫できることがあります。
また、1月末には私立高校の入試が始まりますので、時間を計って速く解く練習をするのも効果的です。
入試までで、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
そのため、自分にとって何をやればよいかをよく考えて、効率よく勉強してください。
いずれにしても、冬休みからは入試本番を意識して、実戦的な勉強法を取り入れましょう。
2-5.3学期は直前対策として過去問を多く取り入れましょう
3学期は、1月末にマークシート形式の私立高校入試があります。
その前後で学習内容が異なりますので、さらに2つの期間に分けて考えましょう。
私立高校の入試はマークシート形式ですので、選択肢を選ぶコツやマークシート記入の注意事項が重要になります。
一方、県立高校の入試では、国語の作文、英語のリスニング、数学の作図や証明問題、理科、社会の記述問題など、記述形式に対する対策が必要です。
どちらの期間も、過去問や予想問題を多く演習して、本番入試に対する「勘」を養うことを意識しましょう。
2-5-1.1月は私立高校対策を中心にしましょう
冬休みのすぐあとか、翌週には学年末テストがあります。そのため、まずは、テスト範囲を意識した勉強をしましょう。
学年末テストが終わってからは、過去問の演習です。
受験する高校の過去問を2~3年分は解いておくことが望ましいです。
過去問を演習する時には、ぜひとも、入試に使われるマークシート用紙のコピーを入手して、記入の練習をしてください。マークシートの記入ミスや誤読で、思わぬ失敗をすることがあるからです。
また、学校によって、マークシート用紙がA4版であったり、横長のカード式であったり、形式が異なることがあります。
自分の受験する高校の用紙に合わせて、練習しておく必要があります。
さらに、選択肢を選ぶときのコツとして、正しくないものを除いていく「消去法」を利用すると、解答の仕方が楽になります。
この時期の練習で、ぜひ効率よく解答できるようにしておきましょう。
多くの生徒にとって、私立高校は第一志望ではないかもしれません。それでも、私立高校の入試結果は、その後の受験勉強や県立高校の志望校決定に、精神面で大きく影響します。
私立高校の入試もたいせつに取り組んでください。
2-5-2.2月から入試までは県立高校対策に集中しましょう
私立高校の入試が終われば、いよいよ県立高校対策の期間になります。この期間は県立高校の過去問を演習することが最重要課題です。
ぜひ5、6年分は解いてください。
さらに、予想問題や、そっくり模試なども演習できると、より成果があがります。
県立高校の入試問題は、毎年同じようなパターンで出題されています。
その形式や傾向に慣れておくことで、本番のテストであがりにくくなるのです。結果として、落ち着いてテストを受けることができ、実力を発揮できるようになります。
卒業生からは、「出題の傾向に慣れていたので、本番でもあわてずに問題を解くことができた」、「当日は緊張せずに、いつもどおりテストを受けられた」という声がよく聞かれます。
もう少し具体的な例をあげると、三重県の入試問題には次のような特徴があります。
これらの項目について、十分に練習しておいてください。
- 国語-物語文、論説文とも記述式の設問が数題ある。200字の作文がある。
- 数学-作図の問題、記述式の証明問題がある。
- 英語-10分ほどのリスニング問題、6問の英作文がある。
- 理科-実験、観察に基づいた問題が中心で、長めの記述問題が複数題ある。
- 社会-地理、歴史、公民のあらゆる範囲から幅広く出題されており、長めの記述問題が複数題ある。
なかでも、国語の作文と英語のリスニングは練習の成果が出やすいので、毎日のように演習を繰り返してほしいと思います。
2月はとにかく、過去問とそれに準じた問題の演習に集中しましょう。
「前日まで学力は伸びる!」ので、最後まで、粘り強く過去問の演習に取り組んでください。
3.塾を活用して効率よく勉強しましょう
これまでの内容をもとに考えていただければ、1年間の受験勉強計画が立てられると思います。
それでもどうしたらよいかわからないこと、うまくいかないところが出てくれば、迷わず塾に相談しましょう。
塾では毎年受験生を指導しているので、受験の実情をよく把握しています。
どの時期にどのような勉強をすればよいか、個々の状況に合わせてアドバイスを受けることもできます。
基本的には、中3の春から塾のカリキュラムに合わせて、計画的に受験勉強を行うのがお薦めです。
しかし、事情によっては、夏からとか2学期から入塾される場合もあるでしょう。
その場合、学力に応じて学習内容を見直さなければなりません。標準のカリキュラムのままでよいのか、遡って学習した方がよいのか、状況は人によって様々です。
塾では長年の経験とノウハウの蓄積があるので、個々のケースに応じて学習計画を対応させることができます。
入塾してからは、計画どおり進行しているかもチェックされますので、お子様を任せても安心です。
受験勉強の中で、「困った」を感じたときは、やはり塾が頼りになりますね。
まとめ
勉強は基礎からの積み重ねがたいせつです。
特に高校受験の勉強では、基礎から始めて、どの時期に、どのような勉強をすべきかを、はっきりさせる必要があります。
そのために、入試日から逆算して、期間を区切った学習計画を立てることが重要です。そして、その計画を確実に実行しなければいけません。
自分では計画が立てにくい、あるいは、計画を立ててもその通り実行できそうにないと感じたら、早い目に塾に相談されることをお薦めします。
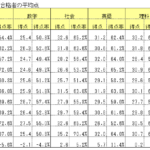

コメントを残す